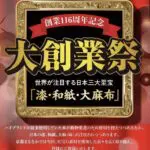皆様、こんにちは( ^ω^ )
いきなりですが、
NHKの朝ドラ『ばけばけ』見られてますか?
お客様の話題にもよくでるんですが、
着物の着こなしが注目を集めていますね★
明治時代を舞台にしているため、
現代の着方とだいぶ違いがでていますね。
(C)NHK
『ばけばけ』に登場する女性たちの着物の着付けは、
特に、半襟(はんえり)を広く見せる着方が特徴的です。
これは明治時代の着付け方で、
現代の人から見ると「半襟が広すぎるのでは?」と感じます。
これも理由があるみたいです!
ドラマの設定は1875年(明治8年)頃。
日本が急速に近代化を進めていた時代で、
当時の着物は反物の幅が現代より狭かったため、
抱き幅もかなり狭くなる寸法だったと考えられています。
半襟を広く見せる着方にも理由があり、
当時は髷(まげ)を結って頭を大きく見せたり、
裾にお引きずり(裾を地面に引く着方)で
綿を詰めてボリュームを出したりしていました。
そのため、全体のバランスをとるために
半襟をたくさん見せることで、
首元にもボリュームを出していたと考えられています。
(C)NHK
また、明治時代は半襟が自己表現のポイントであり、
非常に流行しました。
半襟だけでお店が成り立つほどだったそうです。
びっくりですね(*´Д`*)
現代の着付け教室では、
白い半襟を見せるのは2センチほどとされ、
シャープで知的な印象を与える着方が一般的ですが、
明治時代とは髪型も大きく異なるため、
着付け方も変化しています。
私も個人的には、
柄の半衿や刺繍の半衿を付けた時は
見せる幅を広くする着方で
コーディネートを楽しんでいます。
半衿も、半衿として売っている物に限らず、
好きな生地を付けたりしています。
朝ドラに限らず、着物の柄には
古くから様々な意味や願いが込められています。
無病息災、子孫繁栄、
長寿、富貴、幸福などを願う日本人の心の表れです。

古くから日本人は、四季折々の自然や動植物、
幾何学模様などに特別な意味を見出し、
それを衣服に取り入れてきました。
農耕民族として自然と深く関わってきたため、
季節の移り変わりや自然の恵みに感謝し、
その象徴として柄に意味を持たせたと考えられます。
また、着物の柄には、
着る人や贈る人の願いが込められています。
例えば、子どもには健やかな成長を願って
麻の葉柄の産着を着せたり、
嫁ぐ娘には幸せを願って手毬柄の着物を
持たせたりする風習がありました。
矢絣柄も、一度放たれた矢が戻らないことから、
結婚の際の縁起柄とされ、
嫁入り道具に使われていたこともあります。

⚫︎代表的な柄とその意味
(鶴)長寿と夫婦円満の象徴です。
つがいの鶴が一生を添い遂げる習性から、
結婚式の色打掛など、おめでたい席でよく使われます。
(亀)甲長寿や縁起の良い象徴で、
厄を払い身を守る意味があります。
(松竹梅)それぞれ不老長寿、成長、高潔の象徴です。
(麻の葉)成長が早くまっすぐに伸びることから、
魔除けや子どもの健やかな成長を願う意味が込められています。
(唐草)蔓草が絡み合う様子から、
長寿や子孫繁栄を意味し、
お祝いの着物によく使われます。
(青海波(せいがいは))波が穏やかに広がる様子から、
平穏な暮らしが続くことや、
永遠の幸福を願う意味が込められています。
(牡丹)百花の王とされ、幸福、富貴、高貴、
豪華さを表す縁起の良い花です。
女性の美しさを象徴する柄としても人気があります。
これらの柄意味も知っておくと、
見るポイントも変わってきそうですね。
〜お知らせ〜
今月、10月24日(金)〜28日(火)まで開催される
『大創業祭』に「ばけばけ」に衣装協力されている
小紋屋 高田勝 来場!!!

(C)YouTube 小紋屋高田勝
「ばけばけ」意外にも今話題の映画「国宝」や
朝ドラ「まんぷく」「ごちそうさん」
「カーネーション」などにも衣装協力、
衣装制作、美術協力、呉服指導もされています!!
ご来店の際は必ずご予約が必要となります。
詳しくはお問い合わせ下さいませ。
お待ちしています(^O^)
お問合せ・ご予約は → こちらから ←